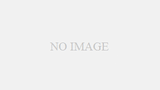結論ですが、
分娩予定日の計算方法として、「最終月経開始日」「排卵日」「胎児の大きさ」などから計算する方法があります。
最終月経開始日から
分娩予定日は、基本的には「最終月経開始日」から計算します。
最後に月経が始まった日つまり「最終月経開始日」を「妊娠0週0日」とします。
この日を基準にして、「妊娠何週何日」なのかを数えていきます。
月経周期が28日型で、排卵周期も規則的に来ている人を想定すると…
妊娠2週0日が「排卵日」、妊娠4週0日が「次の月経予定日」、そして妊娠40週0日が「分娩予定日」に当たります。
実際には、次の月経予定日から1~2週間くらい遅れたタイミングで妊娠検査を行うことが多いため、妊娠5~6週頃に受診される妊婦さんが多いです。
そして、「最終月経開始日」を「妊娠0週0日」として、「妊娠40週0日」にあたる日を「分娩予定日」として計算するのです。
実際には、カレンダーを確認して分娩予定日を算出するのは大変なので、自動計算機を使用して計算することが多いです。
分娩予定日は、基本的には「最終月経開始日」から計算するのです。
排卵日から
分娩予定日は、排卵日を「妊娠2週0日」として計算することもあります。
妊娠週数は、基本的には最終月経開始日から計算することが多いです。
ただし、不妊治療などで排卵誘発をおこなっている場合など、明らかに排卵日がわかる場合には排卵日から分娩予定日を計算することもあります。
最終月経開始日からの計算では妊娠週数がズレてしまうことがあるため、不妊治療などによって「排卵日」がわかっている場合には、排卵日から妊娠週数を計算することもあります。
つまり、分娩予定日は「排卵日」を妊娠2週0日として計算されることもあります。
胎児の大きさから
分娩予定日は、「胎児の大きさ」から計算して修正することがあります。
妊娠週数は、基本的には最終月経開始日を「0週0日」として計算しますが、月経が不規則・排卵日がズレるなどが原因で、実際の妊娠週数とズレてしまう可能性もあります。
そのため、赤ちゃんの大きさを測定して、そこから算出される妊娠週数とズレがないか確認します。
「CRL」(頭殿長)という赤ちゃんの座高のようなものを測ったり、「BPD」(頭横囲)という赤ちゃんの頭の横幅を測ったりします。
おおよそ妊娠8週頃に、「最終月経開始日からの妊娠週数」と、「赤ちゃんの大きさからの妊娠週数」をみて、妊娠週数を確定します。そして「妊娠40週0日」にあたる部分が、分娩予定日として計算されます。
ちなみに、「分娩予定日」ちょうどに赤ちゃんが生まれることは実際には少ないです。
分娩予定日は、「胎児の大きさ」から計算して修正することがあるのです。