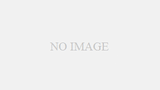多のう胞性卵巣症候群
不妊症の原因として「多のう胞性卵巣症候群」があります。
多のう胞性卵巣とは
「多のう胞性卵巣」は、小のう胞(小さな袋)が多くみられる卵巣のことをいいます。
「排卵」しない状態や、卵胞がうまく発育されないと、卵巣に小のう胞が出来ますが、多くみられる卵巣になると「多のう胞性卵巣」と呼ばれます。
多のう胞性卵巣症候群とは
「多のう胞性卵巣症候群(PCOS)」は、「多のう胞性卵巣」に加えて、月経異常などの症状、LH高値などのホルモン異常を認める場合に診断されます。
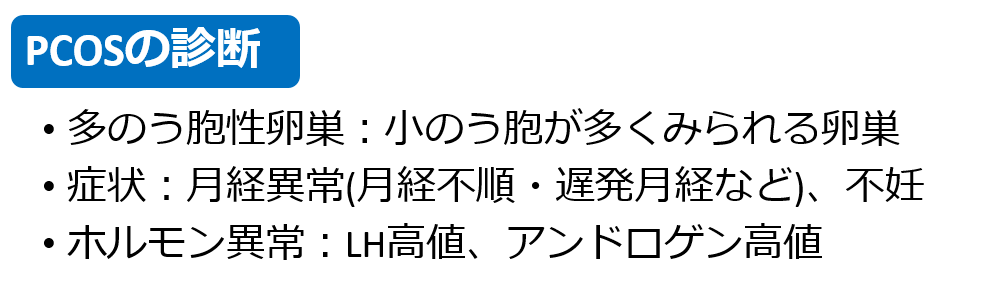
PCOSの検査は
多のう胞性卵巣症候群(PCOS)の検査は、問診、エコー検査、血液検査などが行われます。
基本的には、PCOSの診断基準に応じて検査が行われます。
つまり、問診によって、月経異常(月経不順・遅発月経など)や不妊などの症状の確認、エコー検査で「多のう胞性卵巣」の確認、血液検査で、ホルモン(LH・FSH・アンドロゲンなど)異常の確認をします。
PCOSの治療
多のう胞性卵巣症候群(PCOS)の治療は、排卵誘発剤、卵巣多孔術、糖尿病薬、減量指導などが行われ、妊娠希望がなければ低用量ピル、ホルモン治療が行われます。
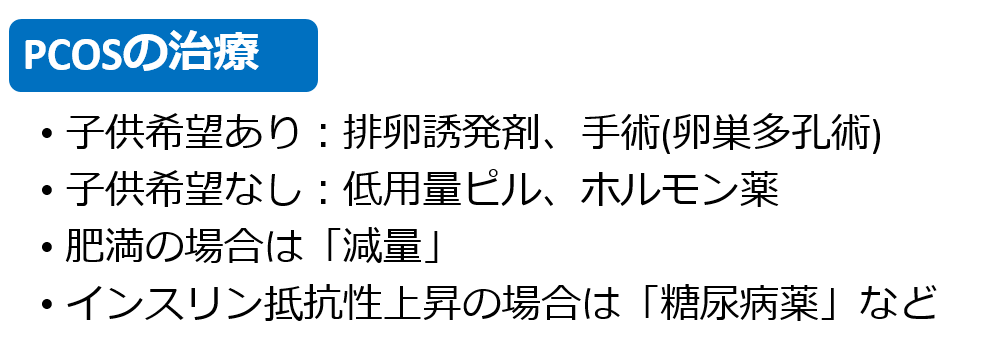
黄体機能不全
不妊症の原因として「黄体機能不全」があります。
黄体機能不全とは
「黄体機能不全」とは、「黄体ホルモン」の分泌が低下することです。
卵巣では「卵胞」が発育し「排卵」します。
排卵後、「卵胞」は「黄体」へと変わり、そこから「黄体ホルモン」が分泌されます。
「黄体ホルモン」は子宮の内膜を受精卵が着床しやすいフカフカのベッドのような状態にします。
「黄体ホルモン」の分泌が低下すると、受精卵は着床しにくくなり「不妊症」となったり、「流産」になりやすくなります。
黄体機能不全の症状
「黄体機能不全」の症状として、「不妊」や「流産」などがあります。
「黄体機能不全」によって「黄体ホルモン」の分泌が低下すると、子宮内膜が着床しにくい状態となり、「不妊症」につながります。
また、受精卵が着床したとしても、十分に育つ前に流れてしまう「流産」につながります。
2回流産を繰り返すことを「反復流産」、3回以上流産を繰り返すことを「習慣流産」と呼ばれますが、その原因として「黄体機能不全」が隠れていることがあります。
黄体機能不全の原因
黄体機能不全の原因は、「脳下垂体の異常」「卵胞発育不全」「高プロラクチン血症」などがあります。
「脳の下垂体」という部分から「LH(黄体形成ホルモン)」が分泌されます。
「LH」の作用によって、発育した「卵胞」は排卵し「黄体」が形成されますが、「LH」が不十分だと黄体がうまく形成されず「黄体機能不全」となります。
なお、卵胞がうまく発育しない「卵胞発育不全」になると、「黄体」が形成されなくなり、「黄体機能不全」となります。
また、「高プロラクチン血症」などのホルモン異常によって「黄体機能不全」となります。
黄体機能不全の検査
黄体機能不全の原因は、「基礎体温」「血液検査」「エコー検査」などがあります。
基礎体温では、通常「低温相」→(排卵)→「高温相」の「二相性」となり、高温相は「12日から14日」続き、その後に月経が開始します。
黄体機能不全では、「低温相」と「高温相」の温度差が0.3度以内だったり、「高温相」が「10日以下(あるいは12日未満)」となります。
血液検査では、「黄体ホルモン」(プロゲステロン)の値を測定します。
黄体機能不全では、高温相における「黄体ホルモン」が低くなります。また、脳下垂体から分泌される「LH」「FSH」、卵巣から分泌される「エストロゲン」(E2)、「T3」「T4」「TSH」などの甲状腺ホルモン、「プロラクチン」などのホルモンも併せて検査します。
エコー検査で「子宮内膜の厚さ」や「性状」を検査します。
高温相(黄体期)における子宮内膜の厚さが不十分の場合、「黄体形成不全」を疑います。
なお、子宮内膜を採取して組織の検査「子宮内膜組織診」を行う場合もあり、正常月経周期と日付のズレがあった場合に「黄体形成不全」を疑います。
黄体機能不全の治療
黄体機能不全の治療は、「原因疾患の治療」「排卵誘発」「黄体ホルモン補充」などがあります。
黄体機能不全の原因があれば、その治療をおこないます。
たとえば、「高プロラクチン血症」があれば、ドパミン作動薬などの治療薬を使います。脳の下垂体にできもの「下垂体腺腫」がある場合には、手術によって摘出する必要があります。
排卵障害があれば、「排卵誘発」が行われます。
クロミフェンやゴナドトロピンなどを使用して「排卵誘発」をおこないます。
黄体機能不全で、分泌が低下している黄体ホルモン(プロゲステロン)を補充します。
高プロラクチン血症
不妊症の原因として「高プロラクチン血症」があります。
高プロラクチン血症とは
「高プロラクチン血症」とは、血液中の「プロラクチン」というホルモン値が高くなり、「乳汁分泌」や「無月経」などみられる疾患のことです。
ただし、「妊娠」「分娩」は、自然と「無月経」となるため除外されます。
また、「授乳期間」は、自然と血液中の「プロラクチン」は高くなり、母乳が出てきて、無月経となるので、その時期も除外されます。
高プロラクチン血症の症状
高プロラクチン血症の症状は、「乳汁分泌」や「無月経」などがあります。
「プロラクチン」というホルモンは、母乳をつくる作用があります。お産が終わって、赤ちゃんが乳頭を刺激すると、「プロラクチン」の分泌量が増加して、母乳が作られるのです。産後、授乳している期間はプロラクチンが増加しているため、基本的には生理は来ない「無月経」となります。
また、「下垂体腺腫」が原因の場合には、「頭痛」や「視野障害」などの症状がおこります。
「プロラクチン」は脳の下垂体という部分で産生されます。プロラクチンをつくる腫瘍「下垂体腺腫」が出来て、「高プロラクチン血症」となる場合があります。そのときは、「下垂体腺腫」による圧迫によって「頭痛」や「視野障害」などの症状がおこります。
高プロラクチン血症の原因
高プロラクチン血症の原因は、「くすり」「甲状腺機能低下症」「下垂体腺腫」などがあります。
以下の薬剤で高プロラクチン血症となることがあります。
「レセルピン」「メチルドパ」「ベラパミル」などの循環器薬、
「ハロペリドール」「クロルプロマジン」などの抗精神病薬、
「イミプラミン」「アミトリプチリン」などの抗うつ薬、
「メトクロプラミド」「H2遮断薬」などの消化器薬
また、「甲状腺機能低下症」によって、「高プロラクチン血症」がおこります。
これは、「甲状腺機能低下症」がおこると、甲状腺ホルモンを産生するように「甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン」(TRH)というホルモンが脳の視床下部から分泌されます。すると、「甲状腺刺激ホルモン」(TSH)というホルモンが脳下垂体から分泌されます。「TSH」が甲状腺に作用して甲状腺ホルモンの分泌が促されます。
それとと同時に「TRH」の作用によってプロラクチンも分泌されるため「高プロラクチン血症」につながるのです。
高プロラクチン血症の検査は?
血液検査
血液検査をして各ホルモンの検査をおこないます。
なによりも、血液中の「プロラクチン」が測定されます。
「無月経」を来たす病気が他にもないか、脳下垂体から分泌される「LH」「FSH」、卵巣から分泌される「エストロゲン」(E2)・「プロゲステロン」(P)などのホルモン検査をします。
また、「T3」「T4」「TSH」などの甲状腺ホルモンの検査もおこないます。
脳MRI検査
「脳MRI検査」をおこなうことで、「下垂体腺腫」がないか検査します。
「プロラクチン」は脳の下垂体という部分で産生されます。プロラクチンをつくる腫瘍「下垂体腺腫」が出来て、「高プロラクチン血症」となる場合があります。
とくに「プロラクチン」が100ng/ml以上の高値の場合、この「下垂体腺腫」の可能性を考えます。
くすりの確認
くすりが原因の「薬剤性高プロラクチン血症」の可能性を考えます。
使用している「くすり」を確認して、プロラクチンを上昇させるくすりがないか確認します。
とくに「循環器薬」「消化器薬」「抗精神病薬」「抗うつ薬」など使用していないかチェックします。
高プロラクチン血症の治療は?
薬物療法
「高プロラクチン血症」の治療には、「ドパミン作動薬」が使われます。
「ドパミン」の作用が増加すると「プロラクチン」の分泌は低下します。つまり、「ドパミン作動薬」によって「プロラクチン」は減少し、「高プロラクチン血症」は改善するのです。
具体的には、「カベルゴリン」「ブロモクリプチン」「テルグリド」などの「ドパミン作動薬」が使われます。
下垂体腺腫の治療
プロラクチンをつくる腫瘍「下垂体腺腫」がある場合には、下垂体腺腫を摘出する「手術」(ハーディ手術)や「放射線治療」(ガンマナイフ)が行われます。
「プロラクチン」は脳の下垂体という部分で産生されます。プロラクチンをつくる腫瘍「下垂体腺腫」が出来ると「高プロラクチン血症」につながります。
その場合は「下垂体腺腫」に対する「摘出手術」や「放射線治療」がおこなわれます。
原因薬剤の変更・中止
「高プロラクチン血症」の原因となるくすりを使っている場合には、そのくすりを変更もしくは中止します。
とくに「循環器薬」「消化器薬」「抗精神病薬」「抗うつ薬」など使用していないかチェックします。「高プロラクチン血症」の原因となるくすりは、原則的に変更もしくは中止します。ただし、治療のために不可欠なものであれば、そのくすりを継続することもあります。
担当医と相談するようにしましょう。
造精機能障害
造精機能障害とは
造精機能障害とは、精子を作り出す機能に異常があり、精子をうまくつくれない状態のことを言います。精巣やホルモンの異常などによって造精機能障害が起こります。
男性不妊の約90%が造精機能障害が原因です。
造精機能障害の種類
- 無精子症:精液中に精子が一つもいない状態
- 乏精子症:精液中に精子はいるが少ない状態
- 精子無力症:精子の数は正常だが、精子の運動率が悪い状態
- 奇形精子症:正常な形態をした精子が少ない状態
造精機能障害の原因
- 精索静脈瘤:精巣温度が上昇し、死滅精子が増加するため
- 停留精巣:精巣温度が上昇し、死滅精子が増加するため
- 染色体異常:Klinefelter症候群など染色体異常による
造精機能障害の治療
明らかな改善できる異常があれば、その治療を優先して行います。
また、精子の量が少ない「乏精子症場合」では、「タイミング療法」「人工受精」「顕微授精」などの不妊治療が行われます。精子が全くない「無精子症」では、「精巣内精子回収」(TESE)などが行われます。
男性不妊の原因2:精子通過障害
精子通過障害とは
精子通過障害とは、精子の通り道が妨げられて、精液の中に精子がいない状態となることを言います。精子は「精巣の中」で作られて、「精巣上体」に蓄えられます。そして性的刺激を受けると「精管」「精嚢」を通り、興奮が絶頂に達すると「射精管」を通って尿道内に入り射精されます。
その精子の通り道に障害が起こると「精子通過障害」となります。
なお、精子通過障害による「無精子症」を「閉塞性無精子症」とよばれます。
精子通過障害の原因
- 精巣上体の閉塞:「精巣上体炎」「Young症候群」などによる
- 精管の閉塞:「先天性」や「パイプカット」「鼠径ヘルニアの手術(幼い時)」などによる
- 射精管の閉塞:「のう胞による圧迫」や「炎症」「外傷」などによる
精子通過障害の治療
精子通過障害は、「精子の通り道を改善する」「精子を回収する」ことが治療方針となります。
精子の通り道を改善するために、詰まっている部分の「開通術」や「再建術」などの手術の適応か判断します。
手術適応でない場合には、精子を回収するために、「精巣内精子回収」(TESE)・「精巣上体精子回収」(MESA)などの治療が行われます。
男性不妊の原因3:性機能障害
性機能障害とは
性機能障害とは、何らかの理由により満足な性交渉をもつことが出来ない状態のことをいいます。性機能障害によって、射精までいかないため、不妊症の原因になります。
性機能障害の種類
- 勃起障害:いわゆるEDのことです。不妊治療によるストレスも原因となる
- 腟内射精障害:マスターベーションで射精可能だが、腟内での射精が困難な状態
- 逆行性射精:精液が尿道口側でなく膀胱側に排出される状態
性機能障害の治療
「勃起障害」や「腟内射精障害」では心理的な要因が大きいため、性交渉をおこなう環境を整えることが大切になります。
また、勃起障害があればバイアグラなどの「薬物療法」、勃起障害・射精障害に対して「人工授精」、逆行性射精であれば、尿中の「精子回収」をして人工授精を行うなどの治療があります。